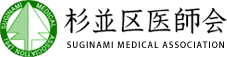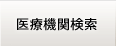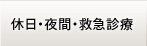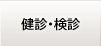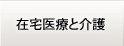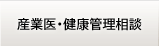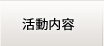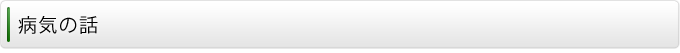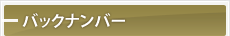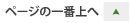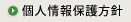�y��114��z
��܊֘A�{����
���e頏ǎ��Â̕��y���i�ނɂ�Ċ{���Ƃ����a�������ɂ���@������Ă��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@���e頏ǎ��Ö�ł��� �@���z���}���܂̃r�X�z�X�z�l�[�g����(�o���܂ƒ��ˍ܂�����܂�)�ƃf�m�X�}�u(6������1�^�@���ˍ�) �� �A���`�����i��p�ƍ��z���}����p�̂Q�̌��ʂ��������\�Y�}�u(1������1�� �A1�N�ԓ��^�@���ˍ�)�̍��z���}����p�ɂ�镛��p�Ƃ��Ċ{�̍������ł��A������������ԂɂȂ邱�Ƃ��܊֘A�{���Ƃ����܂��B
�@�ƕ����Ƌ��낵���a�C���Ǝv�����������������Ǝv���܂����A��܊֘A�{���̔��Ǘ���0.1%, 1000�l��1�l(���s�f�[�^)�ƕ���Ă���܂��B
�@���~�����`�O�ȉ@���@�呺���q �搶���w�˂��w���C�ɂȂ����獜�e頏ǂ��^���Ȃ����x�ɋ���܂���
�@�����̎��Ȉ�t�́u�{�����N����\��������̂ŁA���e頏ǎ��Â��s���Ă���l�͐f�@�ł��Ȃ��v�Ƌ��₵�Ă��܂��̂ł��B�����āA�u������C���v�����g�̎��Â������Ȃ�A���z���}���܂��x�Ȃ����v�Ɗ��҂Ɏw�����Ă��܂��܂��B�������A���́u���e頏�vs���Ȉ�v�̖��ɑ��Ă�2023�N�A�ЂƂ܂����������Ă��܂��B�|�W�V�����y�[�p�[��7�N�Ԃ�ɉ��肳��A�����Ƃ��Ĕ������ɍ��z���}������x�Ȃ����Ƃ���Ă��ꂽ�̂ł��B
�@�����O��2�`3�J���ԁA��p�ʂ̃r�X�z�X�z�l�[�g���܂��x�Ă��r�X�z�X�z�l�[�g�֘A�{���̔��ǂ�����قnj������Ȃ��������Ƃ�A�x��ɂ���č��e頏NJ֘A���܂̃��X�N���㏸���邱�ƂȂǂ��l���������ʁA�x��̗L�p�����m�F����Ȃ��������Ƃɂ��A�ꕔ�̃n�C���X�N�Ǘ�������āA�u�����Ƃ��Ĕ������ɋx��͕s�p�v�Ƃ����V���ȔF���Ƃ��Ċm������܂����B
�@(����)�����̐��`�O�Ȉ�Ǝ��Ȉ�͋������č��e頏ǎ��ÂƎ��Ȏ��Â��ɍs������ɂȂ����܂��B
�@�{���Ƃ����a������l���������Ă��܂��@��������ɕs���������Ă�������吨����������Ǝv���܂����A���e頏ǂ̎��Â��Ă��Ă��A�n�C���X�N�̕��������ẮA�ނ�݂ɋx�Ȃ��Ă����̎��Â�����̂ł��B
�@���Ǝ��̌��N���ێ����邱�Ƃ͌��N�����̉��L�ɑ�Ϗd�v�ł��B������@��ɐ�����������[�߂Ă��������F�l�̌��N���i�̈ꏕ�ɂȂ�K���ɑ����܂��B
[�g�������͉��L�o�Tp123�`p125������p]
�o�T
���ҁ@�呺�@���q�@�@
�w�˂��w���C�ɂȂ����獜�e頏ǂ��^���Ȃ����x�@�@���~��
�ߘa7�N7��
���~�����`�O�ȁihttp://www.sanyuukai.com/�j
���c�@����